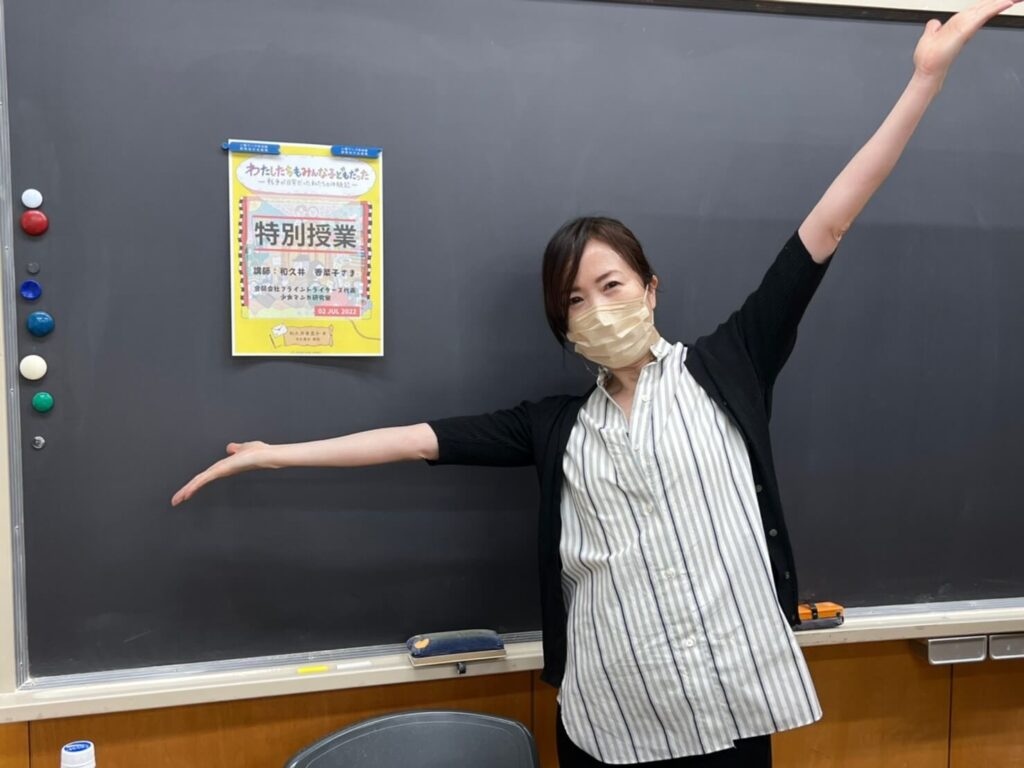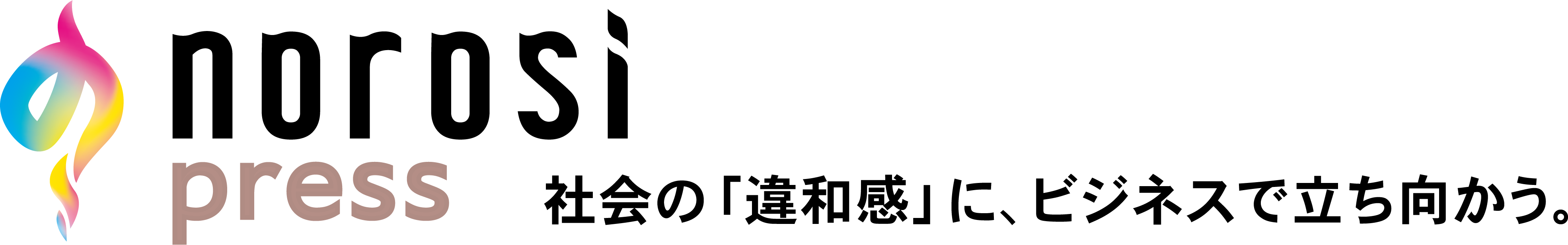少女マンガ研究から事業開発まで。「アイデアを持ち込みまくる」ライターから学ぶ、企画の育て方
すべてのビジネスは一つの「企画」を立てることから始まります。
まだ注目されていない社会課題や不合理にスポットライトを当て、社会に新たな価値をもたらそうと奮闘するスタートアップにとって「企画力」は必須です。
今回お話を聞いた和久井香菜子さんは、フリーランスライターとして多くの雑誌・webメディアで執筆しながら、「合同会社ブラインドライターズ」の代表を勤めています。
ライターと事業家、2つの顔を持つ彼女の仕事のやり方は「様々な企業に企画を提案しまくる」というもの。過去には企画の持ち込みをきっかけに携帯ゲームをリリースするなど、ライターという枠にとらわれず幅広いジャンルで活躍しています。
企画を起点として新しい仕事を生み出し続ける彼女に、企画の発想方法や企画を形にする原動力を伺いました。
| 和久井 香菜子
編集・ライター。主に医療情報、ジェンダー問題について取材・執筆している。早稲田大学第二文学部の卒業論文で「少女漫画の女性像」を論じたことをきっかけに、少女マンガ研究家としても活動している。障害者が活躍する編集プロダクション合同会社ブラインドライターズの代表を務める。 ▶︎プロジェクト:https://www.triven.app/projects/378 |
20代で出会った女性の言葉が「チャレンジする勇気」をくれた
ーー和久井さんのお仕事は「企画を作って、編集部や企業に持ち込む」というやり方だと伺いました。企画の持ち込みはとてもハードルが高そうに見えますが、いつ頃からそのスタイルでお仕事するようになったのでしょうか?
和久井さん:はじめて持ち込みをしたのは20代の後半、フリーランスのライターになって少し経ったあたりです。「せいろの中の点心をお世話して育てる」という育成ゲームのアイデアが急に湧いてきて。プログラミングもゲーム制作も未経験だったのですが、「このアイデアは絶対に面白い、絶対に形にする!」という情熱だけはありました。
どういうプロセスを踏んだらゲームが作れるかもよく分からないまま、とりあえずコピー用紙に鉛筆でマンガを書いて、色々な会社に持っていきました。今振り返ると、企業に手書きの企画書を持ち込むなんて、とんでもない怖いもの知らずだったと思います(笑)。もちろん断られた会社もありました。
それでも「お世話するとワンタンがシュウマイに、シュウマイがギョウザに変身します。これをゲームにしたいんです!」と提案して回っていると、幸運にもインターネットプロバイダのSo-netが拾ってくれたんです。最終的に「養殖中華屋さん」という携帯ゲームとして、世の中にリリースされました。

ーーはじめての持ち込みだったにもかかわらず、大きな仕事を形にされたんですね。仕事の進め方はどこから学んだのでしょうか?
和久井さん:20代のときにお世話になっていた女性から、今の仕事のスタイルを学んだ気がします。
当時の私は、やりたいこともなく頑張れることもなく、転職を繰り返していました。プライベートでも離婚したり、世界で一番ダメ人間だと思っていたんです。でも彼女はそんな私に「あなたにはクリエイティブの才能がある。どうしてその才能を使わないの?」と励ましてくれました。
「あなたはなんにでもなれる」なんて言われたことなかったので、その言葉にすごく勇気をもらいました。そこから前向きになり、「まずは裾野を広げようね」と言われたことで、とにかくなんでもチャレンジしてみようと思えるようになりました。
企画の持ち込みが通って仕事になるのはせいぜい提案したうちの1〜2割で、通らない企画の方が圧倒的に多いです。それでも、活躍している人の話を聞くと、みんなすごくチャレンジしているし、失敗もしている。失敗からどう学ぶかなんだなと思うんです。
企画アイデアの源泉は「正義感」?
ーー和久井さんは記事・書籍・ビジネスなど、幅広い領域で常に新しい企画の種=アイデアを生み出しています。新たなアイデアの着想はどこから生まれるのでしょうか?
和久井さん:知ったかぶってすましているより、色々なことに興味を持ってウキウキしている方が楽しいし、世界が広がるなと気づいたんです。かつ効率中毒なところがあるので、「これとこれを組み合わせたら効率がよくなりそう」「この掛け合わせで新しいことができそう」と考えるのが好きなんです。
また「社会はこうあるべきなのに、そうなっていないのはなぜ?」という、怒りや正義感のような気持ちがきっかけで企画が生まれることも多いです。
たとえば新型コロナウイルスが流行った当初、情報が錯綜していて、何が正しいのか、分からないことがたくさんありました。そのときはSNSで情報発信をしているお医者さんたちに連絡をして、編集部には記事提案して、たくさん取材しました。分かりづらいならマンガにすればいいじゃない! と「コロナマンガ大賞」というコンテストも開催しました。
現在「合同会社ブラインドライターズ」の代表として目に障害を抱えているスタッフとともに事業を行っているのも、社会に対するクリティカルな気持ちが根底にあります。

ーーブラインドライターズを創業したのは、和久井さんが視覚障害者の方にテープ起こしを依頼されたのがきっかけだと伺いました。
和久井さん:短期間で大量の文字起こしをしなければならない案件があって頭を抱えていたときに、知人から「いい子がいるよ」とロービジョンの松田昌美さんを紹介されたんです。納品された原稿を見たところ、自分よりクオリティーの高いものが上がってきてびっくりしました。
そこから自分の取材音源の文字起こしをお願いしたり、知り合いの編集部を紹介したりしていたら、彼女を紹介してくれた方が「ブラインドライター」という名前をつけて、サイトを作ってくれたんです。それがSNSでバズって、そのうち彼女が受け切れないくらいの依頼が来るようになりました。そこでスタッフを少しずつ増やして、ブラインドライターズという団体のサイトを作り、事業として運営するようになりました。
私はそこの管理担当として、クライアントとのコミュニケーションやライターへの仕事の割り振りなど、裏方的なサポートを行っていました。
ーーライターとしての仕事で松田さんと出会ったことがきっかけだったのですね。顧客のニーズがあることはわかっていたものの、ライターと兼業で新たな事業を立ち上げるのは覚悟がいることだったと思います。チーム化を経て2019年に法人化まで歩み続けた原動力はなんだったのでしょうか?
和久井さん:法人化したのは、単純に売上が上がり、消費税納税者になったからです。同時に視覚障害を持つスタッフたちと関わるうちに、障害者の問題も見えてきました。
障害者雇用と言っても別会社での就労だったりして、日本ではインクルーシブがあまり進んでいないと感じます。ブラインドライターズの説明をしてもまったく理解できない人がいるくらいです。社会で自立して働いている、もしくは働きたいと思っている障害者がいるという発想がないのかもしれません。
実際に一緒に働いてみれば、責任感を持ってクオリティの高い仕事をする人がたくさんいることが分かります。彼らが能力を発揮できないのは社会的な損失だと思います。ブラインドライターズのクライアントは大手出版社や放送局などメディアが多く、スタッフたちも社会貢献している実感をしながら働いています。
自分としては「依頼が増えて売上が上がったので法人化した」くらいの意識で、自然の流れでこうなったと思っていました。でも業務を拡大しない、人を増やさない選択肢もあったと人から言われて、ハッとしました。目の前の課題をどう解決するかという意識で考えているうちにポジティブな方向に向かっていたんですね。
仕事は待っていてもやってこない!

ーーブラインドライターズで代表を務める中で、ご自身の「企画力」が活かされるシーンはありますか?
和久井さん:会社の管理や仕事の仕組み化をする際に「こうしたらもっと良くなるのでは?」と考えるのが楽しいです。現在はSlackやDropbox・独自で開発した文字起こしアプリなどのツールを活用しながら、業務やコミュニケーションの質を上げるための仕組みを整備しています。
ーー和久井さんは現在、新たなプロジェクトに取り組もうとされていると伺いました。どんなプロジェクトでしょうか?
和久井さん:全国にある買い手がつかなかったり、取り壊されたりする古民家に着目したビジネスアイデアです。魅力的な歴史(ストーリー)が眠っているものを取り上げ、立地や間取りだけではなく、建物の歴史や売り手の人の情報・売却後どのようにリノベーションしたかなど、古民家にまつわる情報を読み物として閲覧できる情報サイトを立ち上げたいと思っています。
日本は建物が古くなると資産価値が下がってしまいます。でもそれでは歴史ある建物がどんどん失われてしまう。「建物の歴史で物件を買う」という新しい価値を創造できないかと考えているんです。
ーー既存のお仕事もある中で、新たな企画に挑戦し続けている姿、すごくパワフルで憧れます……!
和久井さん:ありがとうございます!私は、自分からどんどん企画をして仕事をもらっているのですが、聞いてみると企画持ち込みする人はごく少数だそうです。ということは、持ち込みするだけで、企業にとってはすごく印象に残るのかもしれません。
周囲の活躍している人を見ていると、「恥ずかしい失敗をたくさんしている」と言っています。へこたれないチャレンジ精神が人生を捗らせるんだろうなと思っています。