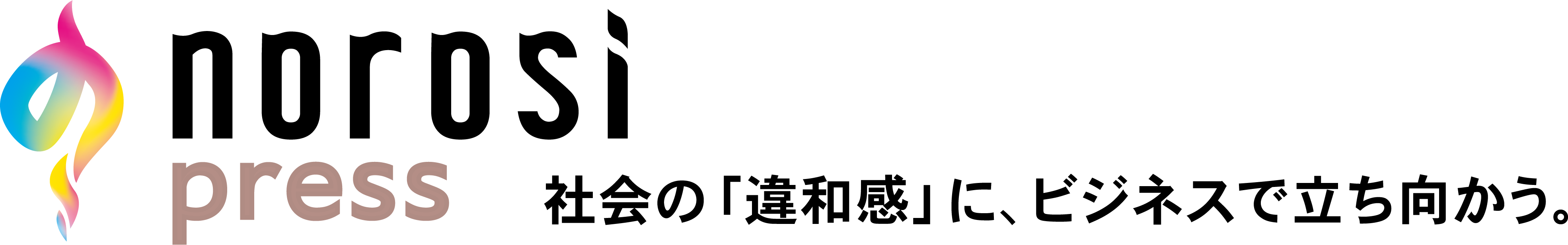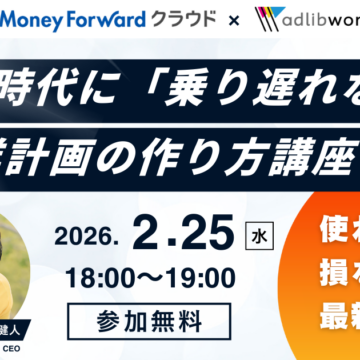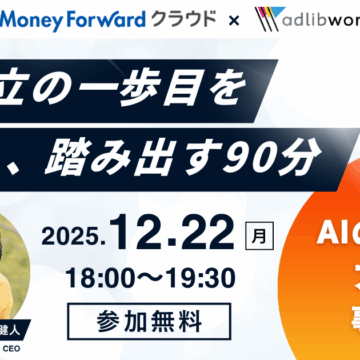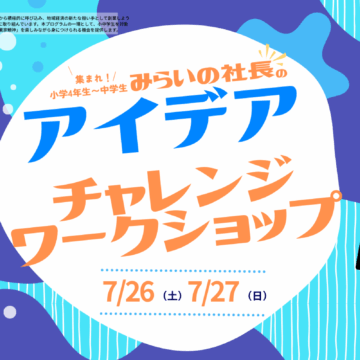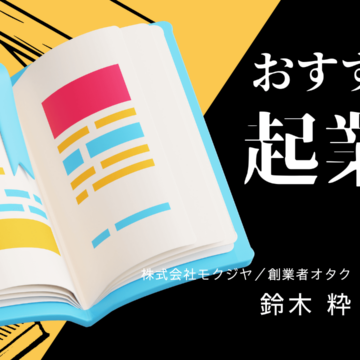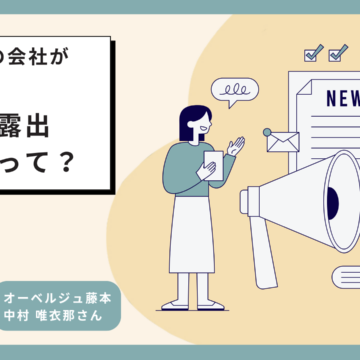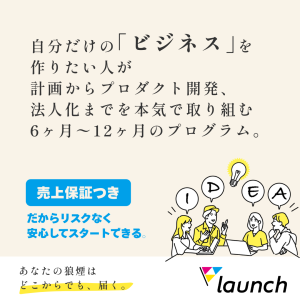起業の資金はどれくらい必要? 資金がない人向けにローリスクな調達方法を解説
起業を考える際、多くの人が最初に悩むのが資金です。
近年のビジネス環境の変化により、起業資金を集めるハードルは下がっています。
この記事では特に資金がない人向けに、効果的な資金集めの方法やリスクを最小化するポイントについて詳しくご紹介します。
起業への第一歩を踏み出すための参考にしてみてください。
起業資金はいくらかかる?

日本政策金融公庫総合研究所の新規開業実態調査によると、2021年度の開業費用の中央値は580万円。1993年の1,000万円をピークに、開業費用は年々縮小傾向にあります。
- IT、web業界を筆頭に、大規模な設備投資が不要なビジネスが広がっている
- クラウドサービスやSNSが浸透し、情報共有や販促の費用を抑えられるようになった
といった理由から、現代では起業の金銭的なハードルは下がっていると言えるでしょう。
とはいえ用意すべき開業資金の金額は、立ち上げる会社の業種によっても変わるため、中央値を気にしてもあまり意味はありません。
起業したい人が考えるべきは、大きく分けて2つ。
・自分の事業をスタートするために、最低限必要な準備は何か?
・起業のリスクを最小化するために、どんな準備をすれば良いか?
「最低限の準備でスモールスタートすること」「リスクを最小化すること」を抑えておけば、起業資金を小さく済ませることができます。
リスクを最小限にする起業のポイント
起業を目指す人が抱える不安は、「売上が上がる前にの転資金が枯渇したらどうしよう?」というものに集約されるのではないでしょうか。
裏を返せば「リスクを少なく、生活資金と運転資金を継続的に獲得する」仕組みを構築することが、起業家の精神的安定につながります。
その仕組みを構築するために必要なアクションとはどんなものなのでしょうか。
クライアントワークを並行して行う
クライアントワークとは、クライアントから依頼を受けて助言や成果物を提供し、対価を得る事業のこと。
代表的な例として「webデザインの受託制作」「システム受託開発」「コンサルティング」などが挙げられます。
もうすでに会社を退職し独立している方の場合、自分の事業(オーナーワーク)と並行してクライアントワークを行うことで、起業のリスクを最小限にできます。
クライアントワークのメリット
クライアントワークのメリットは以下です。
- 自分のノウハウやスキルを元手にするため、初期投資がかからない
- クライアントとの契約が続く限り、売上が安定して入りやすい
クライアントワークの売上をオーナーワークの運転資金として出資できるため、最小限の資金準備や借入で経営を継続できます。
生活資金をクライアントワークで賄えるため、起業後の生活も安定するでしょう。
クライアントワークのデメリット
クライアントワークを増やすと、納期や成果へのプレッシャーに追われ、自分の事業について考える時間が取れないというデメリットも。
クライアントワークは目的意識を持って取り組み、「オーナーワークが大きくなったらクライアントワークを徐々に減らす」など、事業の成長に合わせて仕事をコントロールしましょう。
クライアントワークでおすすめの職種
クライアントワークのニーズとして多いのは「ライティング」「デザイン」「システム開発」「動画編集」といったクリエイティブ系の案件。
ただし上記のスキルがなくとも「採用」「法務」「事業開発」「特定の業界の知識」など専門性があれば、コンサルタントとしてクライアントワークができます。
リスクを最小限にしたい起業家の方は、まずはフリーランスという働き方でクライアントワークを始めてみるのがおすすめです。
クライアントワークの探し方
起業家の中には「自分にはフリーランスで働けるスキルがない」と考える方もいるかもしれません。
しかし社会人経験を積み、また起業しようという意気込みのある方なら、何かしら突出したスキルを持っているはず。
知人に仕事を紹介してもらったり、「ココナラ」「クラウドワークス」などのスポット人材サービス・クラウドソーシングサービスを活用したりすると、気軽にクライアントワークを始められます。
創業融資を味方につける
創業融資とは、これから事業を始める起業家や創業間もない企業が、設備投資や運転資金を確保するために受けられる資金調達制度です。
主に日本政策金融公庫や自治体の制度融資、信用保証協会を通じた銀行融資などがあります。
創業初期は実績がなく信用力も弱いため、通常の融資は受けにくいですが、創業融資は事業計画書や将来性を重視して審査が行われる点が特徴です。
創業融資のメリット
起業時に創業融資を行うメリットとして、下記があります。
- 事業がスタートしてからよりも、開業時の方が融資を受けるハードルが低い
- やりたい事業をスピード感を持って進められる
- 自己資金を温存できるため、経営や生活が安定しやすくなる
- 金融機関と関係性ができることで、お金周りの相談がしやすくなる
「借金が怖い」というイメージから、起業時に借入を避け、自己資金だけでなんとかしようと考える人は多いです。
しかし店舗型ビジネスや大規模な設備が必要な事業の場合、地道にお金を貯めようとすると数年かかってしまうことも。
まとまった初期投資が必要な事業であれば、起業時に借入を行うのがおすすめです。
借入のメリットは「機会の獲得」と「精神的安定」
起業後の事業運営において、適切に投資すれば順調に売上が上がるはずだったのに、自己資金だけで資金繰りした結果資金がなくなり、手詰まりになってしまう悲劇が多くあります。
そして資金が尽きたときに融資を受けようとしても、そのときには信用力が低くなっており貸してくれないことも多いのです。
借入を適切に行い手元の資金を増やすことは、経営の安定だけではなく、起業家の精神的な安定にもつながります。
だからこそ起業時には創業融資を活用し、会社が安定して利益を出しているときに借入をして、資金に余裕を持つことが重要です。
創業融資をきっかけに、金融機関との関係性が深まる
さらに、金融機関と関係性ができることも大きなメリット。
金融機関は様々なビジネスを見て、融資を行ってきたプロフェッショナルです。
そもそも返済が難しくなりそう(実現が難しそう)なビジネスアイデアに対して、無理に大金を貸し出すことはしません。
借入を過剰に不安視しないためにも、「返済可能な見込み額の分以上は貸さない」という金融機関の原則を理解しておくと良いでしょう。
適切に借入を行い返済実績を積めば、企業の信用力も向上し、次回の借入時にも協力してもらいやすくなります。
ビジネスコンテストに挑戦する
ビジネスコンテストは、参加者のビジネスプラン・ビジネスアイデアを審査するコンテスト。
自治体・官公庁が主催していることが多く、ビジネスコンテストによっては「地域課題を解決するアイデア」などのテーマが設定されていることもあります。
ビジネスコンテスト参加のメリット
ビジネスコンテストに参加するメリットとして下記があります。
- アイデアだけで参加できるものもあり、比較的挑戦がしやすい
- 優秀な成績を収めたアイデアには事業化のための支援が受けられる
- ビジネスコンテストで得た賞金を事業資金として活用できる
- ビジネスコンテストで入賞したという実績が評価され、借入や資金調達がやりやすくなる
- 主催する団体や他の参加者との間でつながりが作れる
特に地方では、地域に新たな事業を生み出すことを目指し、様々なビジネスコンテストが開催されています。
コンテストの中には、応募資格に地域的な制限を設けず、幅広く応募者を集めているところも。
ビジネステーマに縛りがなかったり、開催規模が小さかったりなど、参加・入賞のハードルが比較的低いものもあります。
会社員のうちに副業を始めるという選択肢も
まだ法人を立ち上げておらず、サラリーマンとして会社に勤めているのであれば、サラリーマンを続けながら副業を始めるのもおすすめです。
近年は副業規制の緩和が行われ、会社員を続けながら土日や業務時間外に起業準備しやすい環境が整っています。
副業を始めると「会社の給与」という安定収入と「副業収入」どちらも手に入るため、起業資金を貯めやすくなります。
会社員でありながら、副業を通して将来の起業につながるスキルや人脈を得られるのもメリット。
会社員
↓
会社員+副業
↓
副業で得たスキル・知見をもとにフリーランスへ
↓
会社員+副業+フリーランスで貯めた資金を元に起業
と段階を踏みながら少しずつ働き方を変えることで、精神的にも金銭的にも安定感を持った状態で仕事ができます。
起業資金の調達方法|メリット・デメリットも合わせて解説
リスクの少ない資金集めの方法として、下記の方法を紹介しました。
- クライアントワーク
- 創業融資を受ける
- ビジネスコンテストに参加する
- 副業から起業準備を始める
しかし、人によってはこれらの方法をとるのが難しい人もいるでしょう。
ここでは上記で紹介した以外の起業資金の調達方法を、メリット・デメリットを比較しながら解説します。
自己資金(自分の貯金)を使う
起業家の個人資産を自己資金として差し入れる方法です。
- NISAや株式などの金融商品含む保有資産の売却
- 退職金の活用
- 親や親族からの贈与
など、自分の手元にあるお金をビジネスに使います。
起業時の資金調達としては最もオーソドックスな方法ですが、自己資金だけでは足りないことも多く、他の資金調達方法と組み合わせるのが一般的です。
起業で自己資金(自分の貯金)を使うメリット
- 資本を自由に利用できる
- 資金調達先とのトラブルを抱えるリスクがない
起業で自己資金(自分の貯金)を使うデメリット
- 莫大な資金を貯めるには時間がかかる
- 事業清算をした場合、自分の資産を失うことになる
出資を受ける
個人投資家やベンチャーキャピタルから出資を受ける方法。
借入金とは異なり返済義務はないものの、配当金として利益を還元する必要があります。
出資を受けるメリット
- 原則、返済義務や用途の制限がない
- 投資家から経営のアドバイスを得られることがある
出資を受けるデメリット
- 自分の事業に出資してくれる人・会社を探してつながりを作る必要がある
- 株主が経営に関与する可能性がある
- 株主からの出資を受けるためのプレゼンテーションスキルが求められる
補助金や助成金の活用
国や地方自治体の補助金・助成金制度を活用する方法です。
原則返済不要である一方、申請するための書類が煩雑だったり、書類不備で採択されなかったりすることもあります。
申請の際は知識を持つ税理士など、プロをうまく頼るのがおすすめです。
補助金や助成金を活用するメリット
- 原則、返済義務はない
補助金や助成金を活用するデメリット
- 利用用途に制限がある場合がある
- 申請しても採択されない場合がある
- 申請に必要な書類の作成に時間がかかる
- 申請から入金が行われるまでの期間が長いことが多い
- 補助金の場合は後払いのため、手元に資金が必要
クラウドファンディング
クラウドファンディングのサイトに自分の事業アイデアを掲載し、多数の個人から少額ずつお金を集める方法です。
ただし、サイトに掲載しただけで多額の資金を集められるケースは非常にまれ。
多くの場合、知人・友人などに直接クラウドファンディングのお願いをする必要があります。
クラウドファンディングのメリット
- 原則、返済義務はない
- クラウドファンディングを実施することで、広く自社の事業をPRできる
クラウドファンディングのデメリット
- サイト利用料として集めた資金の一部をサイト運営者に払う必要がある
- 知人の応援に頼ってしまうことが多く、事業がうまくいかなかった場合起業家本人が信用を失うケースも
- クラウドファンディングをしてくれた人のために、返礼品の用意が必要
親族や知人などからの借り入れ
起業家の親族・知人からの資金を借り入れる資金調達方法です。
良くも悪くも融通が利く方法である一方で、借金を返済できなくなると大切な人間関係にヒビが入ってしまいます。
実施する際は無用なトラブルを防ぐために「金銭消費貸借契約書」を作成するようにしましょう。
家族や知人から借り入れるメリット
- 資金調達時に厳しい審査がない
- 金額や利息などは、当事者間の合意のもとで自由に設定できる
家族や知人から借り入れるデメリット
- うまくいかなかった際にトラブルになる可能性がある
まとめ
この記事は「起業資金」をテーマに、リスクの低い調達方法を紹介しました。
近年は業務委託という働き方が世の中に広まったことで、副業やクライアントワークを行いながら起業資金を貯めやすくなっています。
また創業融資やビジネスコンテストなど、リスクの低い資金調達の選択肢も広がっています。
様々な調達方法を活用しながら、無理なくビジネスを立ち上げていきましょう。